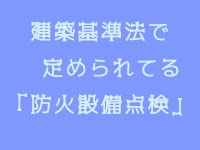
延焼を防止する防火区画の形成し、火災は世辞の安全な避難系をの確保を行う設備が正常に作業するか点検いたします。
- 3種煙感知器
- 熱感知器
- ヒューズ装置
- 防火・防炎シャッター
- 耐火クロス製防火・防炎スクリーン
- 防火扉など
- 連動制御盤(受信機)
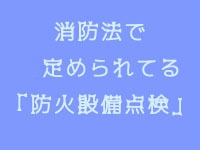 警報により火災発生を知らせたり消火をする設備が正常に作動するかどうか点検いたします。
警報により火災発生を知らせたり消火をする設備が正常に作動するかどうか点検いたします。
- 1.2種煙感知器
- 熱感知器
- 火災報知器
- 屋内消火設備
- 消化器など
概要
- 建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
- 一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
建築物の安全確保のための制度イメージ
〇具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。
〇こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。
調査・検査を行う資格者制度の見直し
消防用設備等点検との違い
「消防用設備等点検」と混同される場合もありますが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で検査資格者も全く異なります。建築基準法を根拠とする特定建築物調査の調査項目に、今までも防火設備に関する項目は含まれていましたが、その調査項目をより強化し特化させたものが防火設備検査と考えるとわかりやすいかもしれません。ですから防火区画等の建築基準法の知識、建築図面への慣れも必要です。報告書様式も特定建築物調査様式に類似しており、提出窓口等も建築物調査と同じケースが多くなります。
建築基準法改正の概要
旧来、防火設備は特殊建築物調査報告の一項目に含まれていました。今回の建築基準法の改正から昇降機や建築設備と同等に検査資格者による定期検査を行う報告対象に引き上げられました。
| 旧来 | 改定後 |
|---|---|
| ・特別建設物(防火設備含む) | ・防火設備(シャッター・ドアなど) ・特殊建築物 |
| ・建築設備(換気、排煙、給排水、証明) | ・建築設備(換気、排煙、給排水、照明) |
| ・昇降機(遊戯施設) | ・昇降機(遊戯施設) |






